情報リソースの信頼性と影響力の関係についての考察
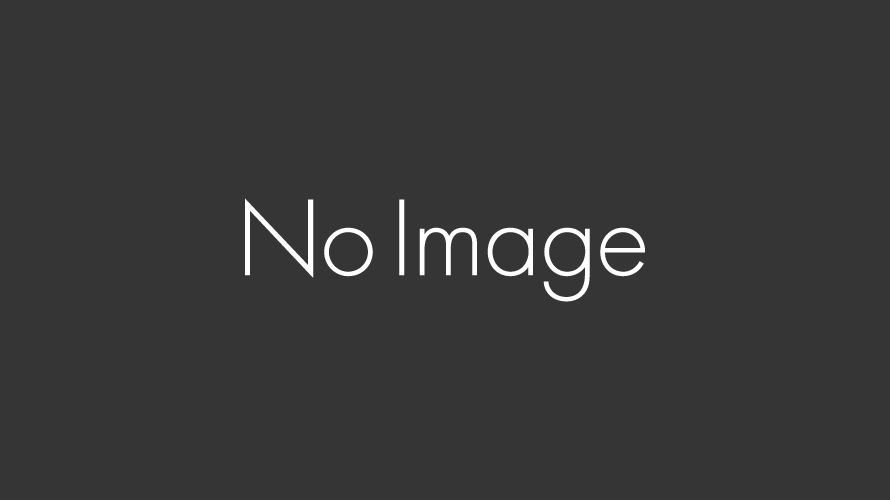
もうすでにこのタイトルを見ておなかいっぱいになってしまった方もいるかもしれませんが、興味をみった方だけ読み進めてください。
これを読まなかったから損するということは決してありません。知らなくても誰もが幸せに暮らせます。
前口上はこれぐらいにしておいて、本題に入ります。
すでにタイトルが物語っている通り、「情報リソースの信頼性と影響力の関係について」考えてみたわけです。
何もそんなことを考える必要もなかったのですが、お客さん先で話をしているときにピン閃いたのです。
似たような話はすでに誰かしているかもしれませんし、知っている人もいるかもしれませんが、
私なりに考えてみたことをまとめてみました。
その前に、「噂」についてお話しいたします。大学で情報社会学という講義の中でそんな話が出ていたことをぼんやりと覚えていますが、
「噂」というのは、どうやって伝わるのかは誰でも知っていると思います。
隣の奥さんや、クラスメイト、同僚などから伝わってくるものがいわゆる「噂」です。
伝達経路は多いようで実はそれほど多くはありません。自分が生活している中で、
かかわりをもつ人からしか伝わらないようになっているのが「噂」なのです。
ちなみに…
噂(うわさ)
とは、その内容が事実であるかどうかを問わず、世間で言い交わされている話の事。類義語として飛語(蜚語)・ゴシップ・デマ・
流言などがある。
(Wikipediaより)
噂の定義には大きく分けて4つあるようですが、その中で流言というものが一般的な噂と考えられます。ちなみに…
根拠はないが、連鎖的に広まるわけなので、そこには何らかのメカニズムが存在すると考えられます。
「自分が生活している中で、かかわりをもつ人からしか伝わらないようになっている」
と前述したのは、そこにこそ情報伝達のポイントが潜んでいるのではないかと考えてのことです。
いきなり話は変わりますが、あなたの尊敬する人をイメージしてみて下さい。
いない場合、よく見る雑誌やWEBサイトなどでも結構です。
そこからの情報というものは割と信用していしまうのではないでしょうか?
たとえば私は、毎朝、日経新聞を読んでいますが、そこからの情報は信用していますし、多くの経営者も同じだと思います。
別にそこから得られる情報がすべて正しく、それ以外が間違っていると言っているわけでも、
日経新聞以外は信用しないというわけでもありません。
では、あなたの親が「志村けん死んだらしいよ」と言ったとするとあなたは信用しますか?仲のいい友達だったらどうでしょう?
実際、そうした形で「志村けん死亡説」
という噂は流れました。
よく知っている人からの話だと、人は簡単に信用してしまいます。それは、その情報リソースに何の根拠がなくてもです。
人間としてコミュニケーションがとれるようになった時から、情報伝達方法の基本は会話によるものです。
会話は人と人とがその場に居合わせればできる究極の情報伝達手段です。また、最も伝わりやすい手段でもあります。
私は、営業という仕事をしているため、さまざまな情報ツールを駆使してお客さんとコミュニケーションを図っていますが、
一番喜んでくれる伝達手法はやはり対面です。そして、私自身も対面によってのコミュニケーション手法が一番安心できます。もちろん、
信頼関係の構築されているお客さんに限りますが。。。
もし、信頼関係がないお客さんに訪問した場合、軽くあしらわれるか、一切取り合ってくれないはずです。嘘だと思うのであれば、
今すぐ見知らぬ土地で飛び込み営業をしてみるといいでしょう。(100件中1件か2件ぐらいは話を聞いてくれるかもしれませんが)
この話はよく営業研修やトップセールスマンの本やセミナーなどで話されている内容なのですが、結局、
情報の伝達も同じことなのだと思うのです。
信頼性の高いリソースであれば、誰もが信用し影響力も絶大でしょう。しかし、
信頼性の低いリソースは見る人はあまりいないかもしれません。
情報リソースは多様化を極め、取捨選択しなければ処理できない時代に来ています。それは、すべての人たちに当てはまりますし、
特に情報を発信する側にとっては大変な時代になってきています。より多くの人たちに情報を伝達したいのであれば、
より信用してもらうことが今後いっそう重要になってくるのではないでしょうか。
-
前の記事
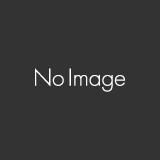
DEATH NOTE 2008.01.14
-
次の記事
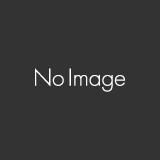
MacBook Air 2008.01.16
