Web2.0
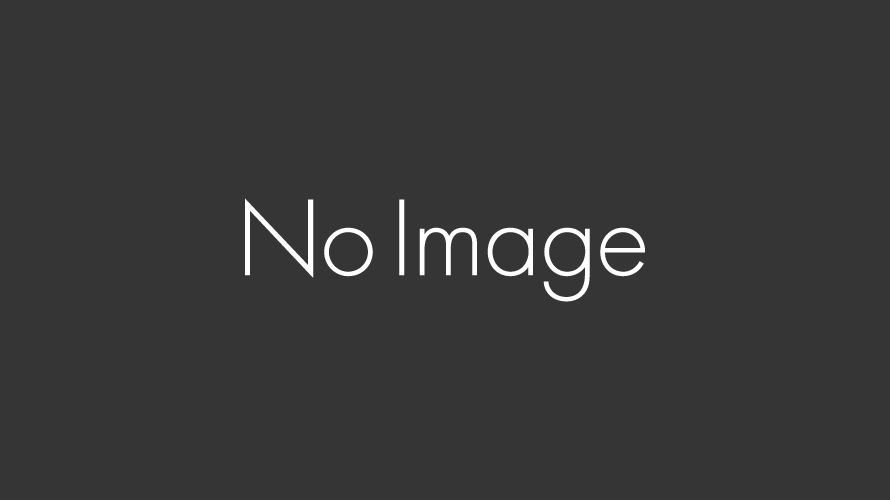
最近、話題になりつつあるものにWeb2.0というものがあります。
流行廃りの激しいIT業界なので新しい言葉が出るたびに、またか・・・と嫌気が指す人もいるかもしれませんが、これは、どうやらもとからあったもののようです。
でも新しい概念なので、新しいのか古いのかと聞かれると良くわかりませんが、一つの考え方としては全く新しいといえます。
もうこの時点で、何のことやら・・・という話ですが、「新しいWebの方向性」といえばなんとなくわかるかもしれません。実際、Web2.0の提唱は行われアメリカでは議論も盛んに行われているようです。
冒頭で新しいのか古いのか良くわからないと言ったのは、既にWeb2.0を私たちは目撃しているからです。
以下は、Web2.0に該当する主なサイトです。良く知っているサイトもあるかもしれません。
- Googleサジェスト
- Googleローカル
- はてなブックマーク
- GREEマップ
- Google PageRank
- 価格.com
- アットコスメ
- Google AdSence
- Amazon
- アフィリエイト
- mixi
- Gree
- Wikipedia
- SETI@home
など
まるで一貫性がないようにも思えるこれらのサイトはすべてWeb2.0の要素を持っているとされています。これらに共通してある要素は具体的に7つあります。
- リッチコンテンツではなくリッチな体験
- ユーザーによる分類:タグ付け
- 誰もが情報ボランティア
- 80:20(パレートの法則)の崩壊
- 情報発信ではなく、情報参加
- ユーザーを信頼する
- 分散化ネットワーク
これらの要素がWeb2.0を考える上で重要な役割を果たします。
これまでのWebはWeb1.0(テキストベースの静的コンテンツ)から始まり、Web1.5(Flashなどを利用したリッチメディアコンテンツ:動的なコンテンツ)を経てWeb2.0(ユーザーを基本とした相互的なコンテンツ)へと進化していったのです。
また、Web2.0を実現するための技術的キーワードもあります。
- XML
- Web API
- Ajax
- Microformats
- Structured Blogging
こうした構造型データフォーマットがWeb2.0であげたような要素を実現可能にします。
このラインナップを見ると、最新の技術で構成されある程度確保された予算も必要となってきます。しかし、現状ではまだそこに投資すべきかまでは見出せないという不安要素もあり、予算確保は難しいと思われます。よって、はじめのうちはオープンソースソフトウェアを利用した形式が一般的になると予測されます。
Linuxをはじめ現在では数多くのオープンソースプログラムの知的資産が蓄えられてきました。日本ではあまりなじみがないですが、海外(欧米・中国)などではその分野の広がりは大きいです。
ただ、重要なのはシステムではなく、あくまでもコンテンツ・アイディアなのです。
-
前の記事
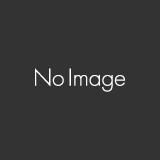
メール対応 Part2 2006.01.18
-
次の記事
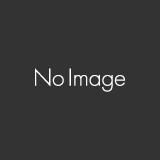
山形まるごと情報サイト ヤマガタウェイ 2006.01.20
